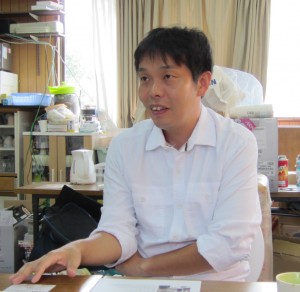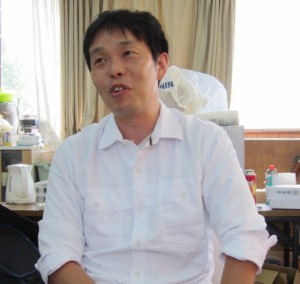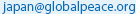HOME > 「多文化」を切り口にまちづくりをすすめる神奈川県営いちょう団地
「多文化」を切り口にまちづくりをすすめる神奈川県営いちょう団地 | 2014.07.18 | Program 1.日本国内の多文化共生の推進
神奈川県横浜市から大和市にかけて広がる「いちょう団地」。2,238世帯の内、約4分の1の430世帯が外国にルーツを持っており、団地内にあるいちょう小学校では、生徒の7割が外国にルーツのある子どもという全国でも有数の「多文化地域」です。
そこで、約20年にわたって「多文化」を切り口にしたまちづくりを進めておられる多文化まちづくり工房代表の早川 秀樹さんといちょう団地の連合自治会会長の栗原 正行さんにお話を伺いました。
―こちらの地域で外国人が多いのは何か理由があるのでしょうか?
インドシナからの難民に対する定住促進センターが大和市内にあり、そのセンターを出た後の住居として、いちょう団地はセンターから近いし、安いし、入居募集数も多かったということで集住が始まったんだと思います。他にも中国の残留孤児の帰国に際して定住地として、神奈川県の県営住宅の中でも最も大きい規模のあるいちょう団地が最初の段階で応募のターゲットになったのではないでしょうか。
―外国人が来られる前というのは空き家が多かったのでしょうか?
空き家も少しずつ出始めていましたし、なにより規模が大きいということがあると思います。普通の団地なら一回の募集で1世帯、2世帯というのが多いですけれど、いちょう団地は最近大分減ってきましたけれど、一時は40世帯、50世帯の募集がかかっていましたので、申し込めばかなりの確率で入れる状況だったと思います。
―もともと外国人はそんなに多くなかったと思うのですが、そこに何年くらいからたくさん住み始めたのでしょうか?もともと住んでいた方との摩擦はありましたか?
私が活動を始めたのが94年なので、その前くらい、80年代後半から90年代に入った頃くらいだと思います。摩擦はいろいろありました。これ以上外国人を入れないで欲しいという要望を行政に出したということもありましたし、反発としてはゼロではなかったと思います。今でも完全に皆が諸手を上げてウェルカムというわけではなく、いろんなご意見はあると思います。
―多文化まちづくり工房を始められたきっかけは何ですか?
私自身は大学時代、中国残留孤児などの帰国者の支援活動団体にかかわっていました。中国の帰国者の関わりのある方の家族が15,6人日本に来るということで、じゃあ日本語教室やっちゃおうかという大学のサークルのノリですね。特に使命感とかあったわけでもなく、「日本語教室はあった方がいいんじゃない?」くらいの感覚でノウハウも何もなく学生だけで始めちゃったわけです。
当時は子どもたちに対しては、何もやっていませんでした。それでも何人かは遊びに来ていたので送って帰ってあげたことはあります。基本的には子供はすぐに日本語をしゃべれるようになるという認識が強かったので、より大人が言葉を勉強できる場づくりが求められていると考えていたのですが、続ける中で子供たちのサポートも必要だと気づかされました。
―外国人を支援する活動をされていく中で一番難しいことは何ですか?
日本語教室や子どもの補習をするにはボランティアの人数が必要です。お金や場所はなくてもなんとかなるケースもありますが、人は絶対に必要。人が来てくれるかどうかというのはボランティアである以上、気持ち次第なので、どうやって関わってもらうかというのが一番難しいところです。関わる人が増えていけば、教室に来る学習者も増えていきますし、ニーズは山のようにあるはずなので、関わる人が多ければ多いほどありがたいです。
―コミュニティの人間関係の中に壁のようなものはありますか?
日本人同士の関係も簡単には越えられない部分があるというか、結構壁が高いのではないでしょうか。大きな部分では外国人との関係の方が壁は低いかもしれません。
もちろんまるっきり壁がないわけではないです。サッカーにしても「3時に集合」と言っているのに4時に来たり、「門を飛び越えて入って来てはいけない」と言っても越えてきたりとかいろんなトラブルもあるけれども、一緒にサッカーやろうと言えば皆集まって来ます。
逆に日本人の方が、「一つのチームじゃないとやりづらい」といった、余計なこだわりがあるのではないでしょうか。
私は「外国人とどうやってうまくやるか」よりは「人として一緒にやっていくには何が必要か」を考えています。個人的には外国人というのはあまり意識していないです。
―活動される中で行政や政策に対する要望はありますか?
あまりないんですよね。そういうのに興味がないので。「自分に何ができるか」ということしか考えていないんです。行政に過大な期待はしていないです。
日本では、外国人も生活保護の対象になっていますし、日本人に対する行政サービスを外国人にも提供していこうという流れがないわけではないので、外国と比べてどうかとかということについては、私では判断しかねるところですし。
―最近諸外国でも外国人の方に対する生活保護などに反発する流れがありますが、国内の外国人への反発に対してはどのようにお考えでしょうか?
実際こちらとしても、彼らに対する疑問や反発を感じることもゼロではないですが、接点を持ってみて、実際に知っている人を増やしてみないと分からないことがたくさんあると思います。何も知らない状態でインターネットやテレビの情報だけで反発を膨らまされても、それもちょっと違うだろうと思いますし。実際話したり、関わったりする中で何か湧き上がるものがあるなら気持ちは分からなくもないですが。
―活動を継続していくモチベーションのようなものは何ですか?
面倒くさいことばっかりで「やっていられない」と思うんだけれど、その「やっていられない」という要素は結構楽しかったりするんですよね。それは始めた頃には気づかなかったですが、続ける中でそれを楽しめるようになってきたのが大きかったです。
子どもにも興味はありませんでしたが、実際一緒に接しているといろいろと「こんな課題もあるんだ」「こんなことを考えているんだ」「子どもはこうやって育っていくんだ」といった色々な面白さがあって、それを私は楽しんでしまっているので。
とにかく普通の人が集まって普通のことをやっているだけで、誰も特別な人間がいるわけじゃなくて、平凡でありながらもちょっと自分が興味あるからという人の方が長続きしやすいんですよね。逆にすごく使命感溢れる人の方が来て数回で消えていくっていうことも多いですね。
消防団にしても「自分の街を守るんだ」という使命感でやっているということもあるかもしれないですが、地域の誰か上の人たちから人足らないからお前も来いよって言われて、「ええ?マジっすか」とか言いながら出て行って楽しかったからまた行くというような形で続けている人が多いんじゃないかと思うんですが。
ここは「日本語教室やってるからおいで」とか「勉強やるから顔出てみなよ」と言える環境がありますが、日本人ばかりの他の地域では日本語教室やるから来いと言ったって誰も来ないわけじゃないですか。ここは切り口として「多文化」というものがあったからそういう場を作りやすかったと思います。だから逆に他の地域はこれから先何を切り口に人の繋がりを作っていくんだろうみたいな思いはあります。
―外国人のスピリットというのは日本人が持っていないものがあって、すごくポジティブだったりとかものすごくアバウトだったりとか、日本人には考えもつかない枠の外のことをやってくれますよね。
たぶん、それは日本人が持っていないというより忘れてしまった文化だと思うんですよね。だからそれをまた取り戻すようなきっかけになるというか、そういう意味ではいい刺激になるんじゃないかと思います。外国人の子どもはフットワーク軽い反面、日本人の子どもはすごく縛りに締め付けられていて、それが今の日本社会の一番の課題なのかもしれませんね。
その他にも、家族や親族の繋がりというものはとても強いものを感じますし、そのネットワークの濃さは日本人の中にはないですよね。そういうことも含めて日本人が彼らから学んで吸収していかなければいけないものも多いと思います。
多文化まちづくり工房としては理念としての多文化共生とか、「外国人をもっと受け入れろよ」という話ではなくて、一緒に作っていかないと仕方がないでしょうという意味で「まちづくり」という言葉を入れています。
―次のステップとしてはどのようなことを考えておられますか?
今、いちょう団地の外国人が流出して、この周辺地域にどんどん広がって第二・第三のいちょう団地ができつつあります。
なぜ流出するかというと、いちょう団地の間取りは狭いんですよ。子どもが増えてくると、ちょっと広い県営住宅に移りたいという人は多いですね。そうなると、外国人の高齢者と日本人の高齢者のみになってしまう可能性も十二分にある地域なんですよね。次の課題が既に目の前に出てきている感じです。
具体的なアプローチとしては、高齢者を繋いでいく作業が必要なのと、もう一つは出て行った若い世代がいちょう団地をどうふり返れるようにしておくかですかね。そのきっかけがサッカーや祭りなのではないかと考えています。
―ありがとうございました
―栗原会長がいちょう団地に入居されたのはいつですか?
1971年の第一期の入居です。当時は、景気も良くて多摩ニュータウンや光が丘など各地に巨大な団地ができた時代でした。
―今は空いている部屋は多いのでしょうか?
県の住宅政策で、50部屋や100部屋くらいはキープしているようです。それらはリーマンショックの時の派遣切りで会社の寮を追い出された人や東日本大震災の被災者の方のために利用されました。今は、春と秋に入居者を募集しています。
―外国の方が増えてきた時はどのような状況でしたか?
当時は政治難民と呼ばれる人や中国残留孤児の人たちが入ってきました。もともと日本は島国で国境線もヨーロッパみたいにあるわけではないので、異文化に接する経験は少ないわけです。当初はトラブルが多発しましたね。当時自治会長をなさっていた金原さんという方が、お互いの理解に努め、仲良く共生するにはどうしたらいいかということでかなりご苦労されたようです。
例えば、集会所での障碍者のクラブがあり、お餅をついて食べていただく企画があって、そこに外国人の方を招待したのをきっかけに食の交流が今も続いています。その集会場で中国やベトナム、カンボジアなどそれぞれの国の料理を作ってもらうことを通して、顔が見える関係ができて、「お母さん元気?」「この間はありがとうね」という感じで段々と仲良くなってきました。その企画は、現在いちょう団地のお祭りの2日目にやっています。
結局、外国人が社会生活の中で学ぶべき内容は、例えば子どもたちが学校で学んで家に帰って「お母さん、ゴミ出しは分別しなきゃ、何曜日には何を出すんだよ」というにように、親は子どもから聞いて学ぶことが多いのです。だから学校の力というのは大きかったと思いますね。子どもたちが学校の指導の下で地域内の清掃をすることを通して、大掃除の手伝いや掃除当番などでも理解を得られるようになってきましたし。
ボートピープルや政治難民という人たちの中には、学歴も身分もある人も多いのです。子どもにもきちんとした躾もするし、そういう人と後から入ってきた人たちというのは違いますね。命からがら逃げてきた人たちは国には帰れないですし、ここが私たちたちの国だという形で帰化するのも早いし、生活を学ぶのも経済的に自立するのも早いです。
しかしそういう人たちはだんだんといなくなってしまいましたね。戸建やマンションを買ったりして出て行くという形で。こちらからすれば結構貴重な人材だったのですが。
―現時点での課題や今後の展望を教えてください。
強いて言えば自治会の活動にあまり参加してくれないということですね。お祭りには顔を出すのですが、運営を一緒にやるというのはなかなか難しいですね。
日本人も外国人も高齢化してきて、我々も70を過ぎていつまでもこんなことはできませんよね。若い人たちもあまり自治会に参加してくれるわけではないので、このまま自治会が成り立たないと行政としても先々窓口が無くなってしまうのではないかと心配しています。
今、メディアで注目されていますが、一番苦しい時には何の興味も示さずなぜ今更になってという気もします。(笑)
これまでいろいろ問題がありましたが、時間が解決したということが多いです。会って、「こんにちは」と言えば言われた方もむっとしてはいられませんし、掃除当番も言われたら「わかりました」と言わないといけません。その辺でお互い顔がつながって言葉をかけあうというところが一番大切だと思います。決してこれは外国人だからというわけではなく、日本人だって同じようにしないといけないわけです。お互いに仲良くした方が利口ですからね。